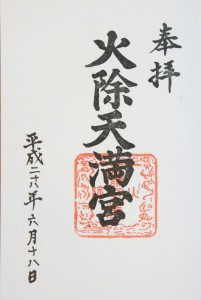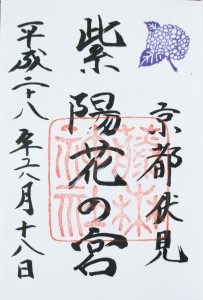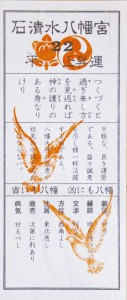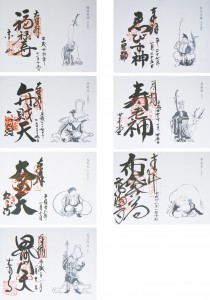昨年7月から、セガレの中学入試合格祈願のため、あちこち天神様を巡りました。
京都の北野天満宮をはじめ、東京近郊だけでも23ヵ所参りました。
その甲斐あって第一志望校に合格することができ、受験後、間もなく御礼参りを始め、先日、ようやく区切りを付けることができました。
拝殿で手を合わせていると、合格祈願のときは心の余裕がなかったな、と感じました。
御礼参りに出向いて、落ち着いた心境で新たに参拝できたことは収穫でした。
湯島天満宮・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(文京区)
久里浜天神社・・・・・・・・・・・・・・・・・・(横須賀市)
亀戸天神社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(江東区)
谷保天満宮・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(国立市)
平河天満宮・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(千代田区)
五條天神社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(台東区)
布多天神社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(調布市)
西向天神社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(新宿区)
成子天神社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(新宿区)
永谷天満宮・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(横浜市)
岡村天満宮・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(横浜市)
牛天神北野神社・・・・・・・・・・・・・・・・(文京区)
荏柄天神社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(鎌倉市)
千葉天神〈千葉神社摂社〉・・・・・・(千葉市)
新井天神北野神社・・・・・・・・・・・・・・(中野区)
大宮天満宮〈大宮八幡宮摂社〉・・(杉並区)
町田天満宮・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(町田市)
徳丸北野神社・・・・・・・・・・・・・・・・・・(板橋区)
(参拝順)
御朱印をいただいたのは上記18ヵ所です。
櫻木神社(文京区)と北野神社(江戸川区)では、あいにく頂戴できませんでした。
一方、受験が終わってからお参りに伺った天神様もあります。
菅原神社・・・・・・・・・・・・(東京都町田市)
東蕗田天満社・・・・・・・・(茨城県結城郡)
大生郷天満宮・・・・・・・・(茨城県常総市)
これで合計23ヵ所になります。
こんなにもたくさんの天神様でご祈願させていただいたんだ、と感慨深い思いです。
「お主、また来たんか!」と道真公に煙ったがられたかも知れませんが……。
しかし、参拝に訪れたい天神様は、全国にまだまだあります。
やはり、日本三大天神は、ぜひとも制覇したいですね。
北野天満宮には参拝させていただいたので、あとは太宰府天満宮と防府天満宮です。
名古屋三大天神の上野天満宮、桜天神社、山田天満宮もいいですね。
それから、大阪の上宮天満宮と福島天満宮も魅力的です。
忘れてはならないのが、仙台市にある杜の都の天神様・榴岡天満宮です。
「東風吹かば匂ひおこせよ梅の花」
この有名なご詠歌が入った「見開き」の御朱印がいただけるのです。
宮城縣護国神社や大崎八幡宮・亀岡八幡宮も巡りながら、お昼は牛タン、食後は「ずんだ餅」。
そんな目論みを、家族には隠密に、そして、着々と進めています…。