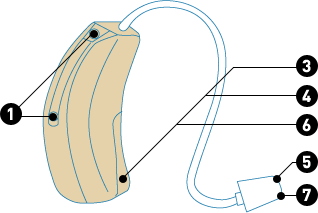昨日、東京オリンピックが閉幕しました。
ライバル都市のマドリードとイスタンブールを破って、開催都市に選出されたのが2013年9月。
IOC・ロゲ会長(当時)の「TOKYO!」から8年近くの歳月が流れたことに驚きました。
私にとっては、自分が生まれ育った町で2度目の開催となるオリンピック。
これはかなり幸運と言ってよいかと思います。
これまでに夏季オリンピックを複数回開催した都市は、パリ、ロンドン、ストックホルム、ロサンゼルス、アテネで、東京を含めても6都市しかありません。
3度行われたのはロンドンのみで、他は2度。
ただ、2024年パリ、2028年はロサンゼルスでの開催が予定されていますので、どちらも3度目となりますね。
前回の東京大会は、1964年10月。
私はまだ3歳でしたので、空に描かれた五輪マークも、東洋の魔女の活躍も、残念ながら記憶に残っていません。
そして、東京2020。
3歳の幼児は、還暦間近のオッさんになりました。
今回はぜひ生で観戦、と思っていましたが、新型コロナの影響で無観客になってしまったのは予想外でした。
自分が住み、働く町で開催されているにも関わらず、どことなく遠くに感じた東京五輪。
交通規制により車の移動が制限され、確かに自国で開催されていた東京五輪。
テレビの前で、今日はどの種目を応援しようかと、独特のワクワク感があった東京五輪。
「過去最多を更新」というニュースに、メダリストか感染者かと迷った東京五輪。
17日間にわたる戦いは、心に残る場面の連続でした。
・バドミントン女子ダブルスで、フクヒロペアを破った中国ペアが、試合後に廣田選手の患部を気に掛け、ハグしたシーン。
・最後の大技を失敗して泣いているスケートボードの岡本選手を、他国の選手が担ぎ上げたシーン。
・ソマリアの難民で若い頃に母国を離れた2人の選手がオランダとベルギーに国籍を移して臨んだ男子マラソンで、2人揃ってゴール前スパートし、銀メダルと銅メダルを獲得したシーン。
1年延期や無観客など、異例づくしのオリンピックだったことの裏返しなのか、国籍や人種、勝敗を超え、健闘を讃えあう場面をたくさん目にしました。
そして、全力で戦ったアスリートたちに、政治的な壁は存在しませんでした。
世界各国から集まった一流選手たちのパフォーマンスに多くの感動を覚えた一方で、国内の新型コロナウイルス感染者数は拡大の一途でした。
パラリンピックがまだ控えていますが、兎にも角にも対策をより強く進めないといけません。
まん延防止等重点措置の適用が、8県に追加されました。
政治家は、これから益々勝負の時を迎えるのだと思います。
そんな中、金メダルを噛んだ某市長には閉口しました。
人を非難するコメントはあまり気乗りがしませんが、「迷惑をかけているのであれば、ごめんなさい」という言いぐさで、許容範囲を超えました。
不快に思った人がいないなら謝る必要はないという論理は、心からお詫びするという言葉と大きく矛盾します。
きちんと謝罪ができない人間に、正しい政治判断ができるでしょうか。
苦しい環境にも屈することなく努力を重ね、金メダルを獲得した勇敢なアスリートの輝かしい功績を汚さぬため、この映像がネット上から早く消えて欲しいと思います。
地位にあぐらをかいた特権意識の消えない政治家。
ひょっとしたら、この改善がコロナ収束のカギを握っているのかも知れません。