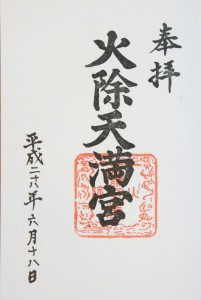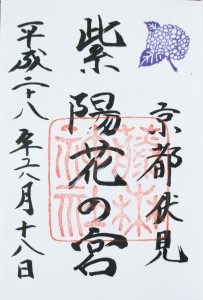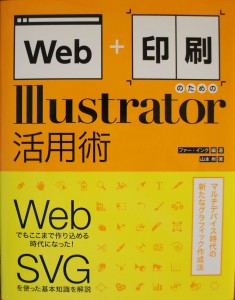以前にも少し触れましたが、私には98歳になる伯父がいます。
大正6年10月15日生まれです。
折しも今日は終戦記念日ですが、伯父は太平洋戦争を経験しています。
一度ならず、何度も出征したそうです。
しかし、これまで、戦争について語ることは、ほとんどありませんでした。
「戦地でいろいろあったから、俺は、晩年幸せな人生は送れないかも知れない・・。」
いつぞや、周囲にそうこぼしたことがある、と聞いたことがあります。
この重い言葉に隠された伯父の胸奥を、私には推し量ることなどできません。
私の好きなノンフィクション作家・門田隆将さんの著「太平洋戦争最後の証言」によると、大正生まれの男子1,348万人のうち、およそ200万人が戦死したそうです。
7人にひとりです。
私もあと40〜50年早く生まれていたら、と考えると血の気が引きます。
伯父は子供が4人いますが、全員女の子でしたので、男の私を大層可愛がってくれました。
私に初めて自転車を買ってくれたのも伯父でした。
伯父の住む田舎の広い庭で毎日何十回も転び、寝る前に二人でスネのアザの数を数えました。
そして、ようやく乗れるようになった夏休みは、今も忘れることができません。
大学に合格した時も、たくさんお祝いをいただきました。
「行きたい学校に合格して良かったね。おめでとう。」と喜んでくれました。
家内を連れて遊びに行ったときは、寿司の出前をとってくれました。
カミさんに気遣いして、持てなしてくれたのだ、とすぐにわかりました。
オレは田舎者だから・・といつも謙抑で遠慮深い伯父でしたから。
また、伯父は手先が器用で、何でも作ってしまう人でした。
削いだ竹を編んで作った器は、職人顔負けの出来映えでした。
そして、腕相撲も強かったし、将棋も上手だった。
少年のボクには、何でもできるスーパーマンのような存在でした。
今秋には99歳を迎えますが、いくつになっても、伯父は私にとってスーパーマンです。
尊敬と感謝の念を込めて、白寿のお祝いを贈ろうと思っています。