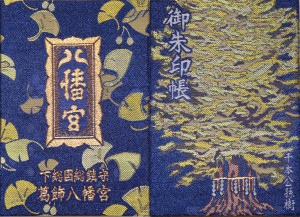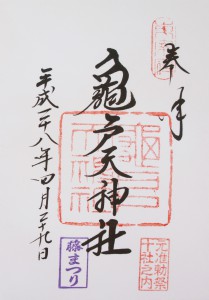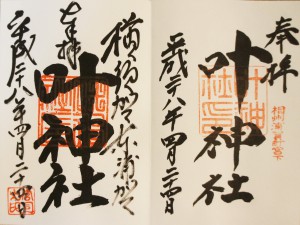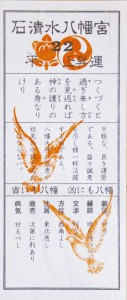ある資料によると、日本にはおよそ822,000人の山田さんがいて、日本の苗字ランキング、第12位だそうです。
印象としては、もうちょっと順位が上でもいいような気がします。
学生時代、周囲には、大抵私以外の「山田さん」がいました。
一番面倒だった思い出は、山田仁美さんという女性がクラスにいたときです。
ちょっと短気な体育の先生が、出席をとろうとして「山田」が混合したらしく、
『やまだまさみ、やまだひとみ、お前はどっちなんだ!』
とご立腹になったことがあります。
私は自分の名前が女性っぽいことを重々承知していますので、こういうことには慣れていますが、やまだひとみさんは女性ですからね、さぞイヤな思いをしたでしょうね。
そして、私には、山田という同姓の親友がいます。
彼の外見上の特徴は、185cmの長身。強面。威圧的。鳩胸。そして、凶暴。低音。
20年以上前、彼とよく飲みに行ったのですが、どちらも山田なので、お店では『大きい山田さん』『小さい山田さん』と、呼び分けられました。
これは正直あんまり気分が良くありませんでしたね(笑)。
で、先日、その大きい山田さん夫婦と焼肉を食べに行きました。
その際、第一志望校合格おめでとう、とセガレに入学祝いをいただきました。
そのほかにもうひとつ、スペシャルでサプライズなプレゼントがありました。
青果市場の店長でもある彼が用意してくれたのは『太陽のタマゴ』。
今年4月7日の初セリで、1箱2玉入りが20万円で競り落とされた宮崎産完熟マンゴーです。
彼曰く、今も有名果実店で、1個15,000円ほどで売られているのだそうです。
54歳にして、ワタクシ、初めて実物とご対面しました。
そして、その味は・・、
濃い!
甘い!!
深い!!!
言葉に尽くせぬ感動的な味でした!
今まで食べていたマンゴーとは、全く違う種類の食べ物でした!
こんな高級品、ゼッタイ自分では買わないでしょうからね。
人生最初で最後の太陽のタマゴかも知れません。
いや〜全く有難いですね。
市場というところには、普段スーパーではお目に掛かれない商品が数多くあります。
特に、彼の店は、一級品を数多く揃えているので、心奪われる商品が所狭しと並んでいます。
見たこともないようなサイズ感の果物だったり、
何かと何かを掛け合わせた見慣れぬ新種だったり、
全く時季外れの商品が当たり前のように陳列されていたり・・。
千住市場の関水青果さんです。
一般の方も入場できます。
でも、市場ですから、午後は閉まってしまいます。
午前中早い時間帯に、ぜひ、足をお運びください。