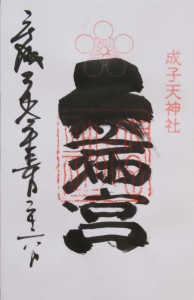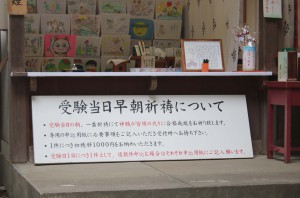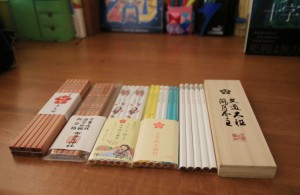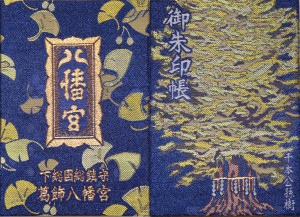平成28年10月27日、三笠宮崇仁親王が100歳で薨去されました。
謹んで哀悼の意を表します。
このニュースが報道されたとき、ほとんどのメディアが「薨去」と報じました。
確か、昭和天皇が亡くなられた際は「崩御」と報じられていたはず‥‥。
なぜ表現が異なるのか、ちょっと調べてみました。
崩御(ほうぎょ)
日本の天皇陛下をはじめ、皇帝、国王、太皇太后、皇太后、皇后、その他君主などが亡くなられたとき
薨御(こうぎょ)
皇太子や大臣が亡くなられたとき
薨去(こうきょ)
皇太子妃、親王、親王妃、内親王、または、*位階が三位(正三位・従三位)以上の方が亡くなられたとき
卒去(そっきょ、しゅっきょ) 王、女王、または、位階が四位(正四位・従四位)、五位(正五位・従五位)以上の方が 亡くなられたとき
*位階とは、長く官職にあった者や特に功績のあった者など付与される栄典の一つで、
第二次世界大戦以降は、故人にのみ与えられています。
これはなかなか難しいですね‥‥。
死去・逝去・永眠・他界・鬼籍に入る。
私のボキャブラリーはこの5つくらいでしたが、どれも皇室には使用しないんですね。
しかも、身分によって使い分けなければいけないところが、非常にデリケートだと感じます。
宮内庁のスタッフはこれら難解な用語がすべて頭に入っているとしたら、恐れ入りますね。
その宮内庁のホームページには「用語集」が掲載されています。
これもなかなかヘビーでしたが、とても興味深い内容でしたので、一部をご紹介します(http://www.kunaicho.go.jp/word/)。
・行幸(ぎょうこう)天皇が外出されること
・還幸(かんこう) 天皇が行幸先からお帰りになること
・行啓(ぎょうけい)皇后・皇太后・皇太子・皇太子妃が外出されること。
・還啓(かんけい) 皇后・皇太后・皇太子・皇太子妃が行啓先からお帰りになること。
・行幸啓(ぎょうこうけい)天皇・皇后がご一緒に外出されること
・還幸啓(かんこうけい) 天皇・皇后がご一緒に行幸啓先からお帰りになること。
おそらく、「幸」や「敬」には皇族が外出されるという意味があるのでしょうね。
私の持っている漢和辞典には、掲載されていませんでしたが‥‥。
いずれにしろ、こういった使い分けが理解できたら、新聞記事が楽しくなるかも知れません。
眞子様や佳子様、愛子様がご結婚される際には、目新しい言葉が紙面を飾るでしょうから。
ちょっと勉強してみようと思っています。
【余談】
「鬼籍に入る」は、「はいる」ではなく、「きせきにいる」と読むのが正解です。