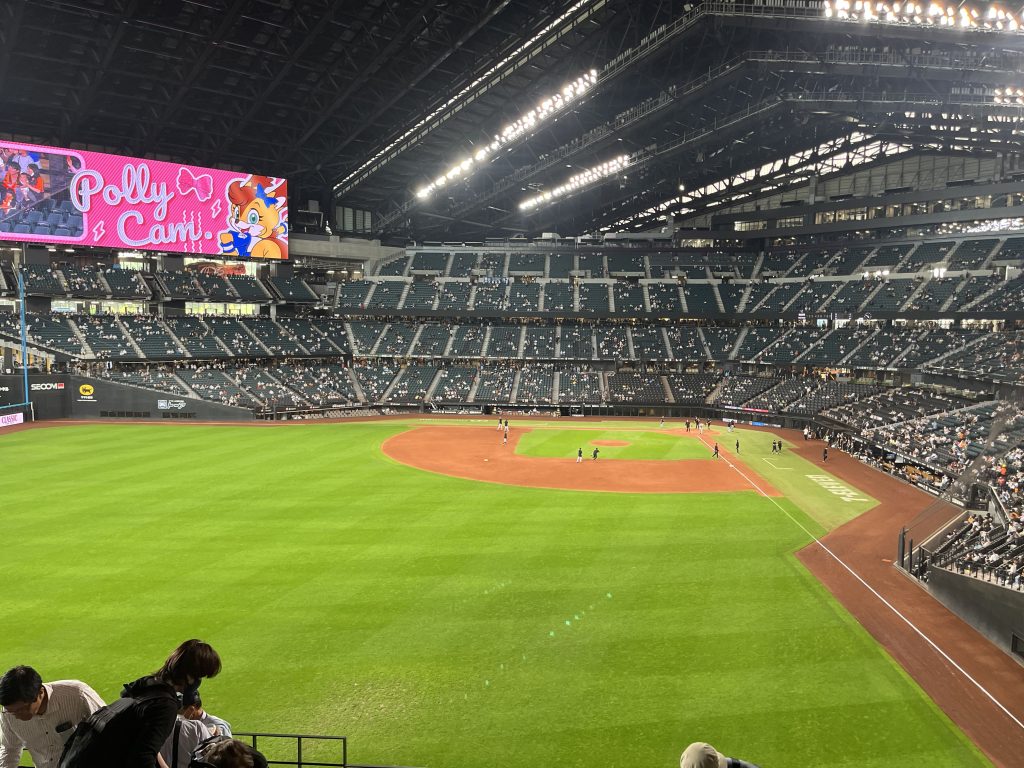私は子供の頃から蚊に刺されやすい体質でした。
そういう体質の存在が医学的に証明されているのかどうかの知見はありませんが、集団の中で真っ先に自分刺されることが多かったのは事実です。
その傾向は、年を重ねても一向に変わりません。
先日、テレビ番組で蚊の特集が組まれていて、蚊にさされやすい人の特徴が以下のように紹介されていました。
- 体温が高い人
- 汗をかいている人
- 濃い色の服を着ている人
蚊は、触覚と口吻という器官を使って温度を感じ取ることができるのだそうです。
どちらかというと、私は体温が高いので、蚊の標的になりやすいのかも知れません。
しかし、特に汗っかきではありませんし、濃い色の服ばかり着ている訳ではありませんので、なんとなく消化不良のような内容でした。
そこで、GoogleのAIモードに「蚊に刺されやすい人の特徴」と入力すると、以下のような回答を得ました。
体質・生理的な要因
・体温が高い人
・汗をかきやすい人
・特定のにおいを持つ人
・呼気に含まれる二酸化炭素が多い人
・血液型O型の人
行動・環境的な要因
・アルコールを摂取した人
・黒っぽい色の服を着ている人
・動きのある人
この時期に「蚊」を話題にした理由は、9月に入ってから、顔を3箇所、蚊に刺されたからです。
仕事から車で帰宅し、自宅マンションの1階でエレベーターを待っているときでした。
4階に停まっていたエレベーターが降りてくるまでのわずか数十秒の間に、こめかみ・あご・おでこ、とやられました。
エアコンの効いた車から降りたばかりですから汗はかいていませんし、当然運動直後ではないし、着ていたワイシャツは白でしたし、エレベーターを待っている間はじっとしていましたし(当たり前)、運転していたのですからお酒は飲んでいませんし(そもそも下戸)、血液型はA型ですし・・。
様々な研究が進んでいるのでしょうが、「蚊に刺されやすい」ことに関しては納得がいかないことだらけです。
これまで、あの小さな生物への敗北感を、何度となく感じてきました。
ところで、「蚊の博士」と呼ばれる方がいるのをご存じでしょうか。
害虫防除技術研究所所長で医学博士の白井良和さんで、蚊の話題になると、雑誌やテレビに頻繁に登場します。
巷でささやかれる「蚊にまつわるウワサの真相」について白井さんが答えている記事が面白かったのでご紹介します。
(https://news.yahoo.co.jp/articles/e3c592f616c8b286e0c26ae4dc1218b2345fc4c4?page=2)
【O型は刺されやすい】
⇒ 実際にO型>B型>AB型>A型の順で刺されやすい。
【太っていると刺されやすい】
⇒ 表面積の大きさや体温の高さ、水分と二酸化炭素の排出量で蚊に認識されやすい。
【赤ちゃんは刺されやすい】
⇒ 生まれたばかりの赤ちゃんは体温が高いので刺されやすいが、抗体がないので痒みはない。
【蚊は黒い服が好き】
⇒ 黒だけでなく、紺色など暗色は認識されやすい。白など明るいゆったりとした服を着ると刺されづらくなる。
【蚊は風に弱い】
⇒ 蚊の体重は2ミリグラム。風で飛ばせるので、うちわやハンディ扇風機をあてると寄ってこない。
【足の裏をアルコールで拭けば全身刺されない】
⇒ 足を拭いても刺されにくくなるのは足のみ。いちばん蚊を誘引するのは顔の皮脂。こまめな洗顔、タオルで拭うなどして。
【蚊は逃げるとき縦方向に飛ぶので、蚊をつぶす際は上下にはたく】
⇒ 考えるより先に、見た瞬間に、方向関係なく蚊をよく見て叩いてつぶすべし。
「蚊にまつわるウワサ」といえば、子どもの頃「蚊に刺されたら爪でバッテンを付けるべし」と言われていましたよね。
どうやらこれは、患部を傷つけて症状が悪化する可能性があるのでNGなのだそうです。
バッテンを付けるとどことなく気持ちいいので、しばらくは引っ掻かなくてもいられる、という意味においては効果があるんじゃないか、と思ったりもしますが・・。