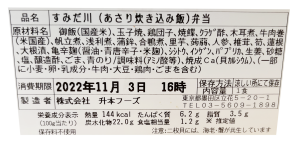昨日、小学校時代の友人5人で集まりました。
転校生の私は2年短くなりますが、かれこれ55年近くの付き合いになります。
正に、総角之好(そうかくのよしみ)。
小さい子どもの時分からの長く親しい交際です。
こんなにも長い間、友であり続けることは奇跡とも言えますし、有難いことです。
これまでの会合は居酒屋を本拠地としてきましたが、今回はフランス料理店に舞台を移し、アラカルトをいただきました。
年齢とともに呑む量が減ってきており、飲み放題とは縁遠くなってきました。
ときに、ずいぶん昔のことですが「長い間、友人関係を継続できる要因」について特集した雑誌を読んだことがあります。
誤っている部分があるかも知れませんが、粗々以下のような内容であったと思います。
①自然体でいられる
②連絡を絶やさない
③干渉しすぎない
④馬が合う
⑤共通点がある
早速、我々に当て嵌めてみたいと思います。
まず、小学校時分からの知り合いですから、超自然体です。
親や兄弟のことなど細かいことまで周知の間柄ですから、今さら格好の付けようがありません。
連絡という点では、年賀状でずっとつながってきましたし、反面、干渉し過ぎることはこれまで全くありませんでした。
また、ちょっとお下品な話になると殊のほか盛り上がるところは、馬が合うと言えます。
ただ、共通点という要因には、課題が残ります・・。
小学校の同級生である我々は、中学受験に失敗した私を含め、地元の同じ区立中学に進学しましたが、その後の人生はバラエティに富んでいます。
女子なのに黒いランドセルを背負っていた☆☆江ちゃんは、美容師となり、20代前半に結婚。
早くもお孫ちゃんが4人います。
近年転ぶことが多く、整形外科外来の常連です。
☆☆子ちゃんは、バブル期を謳歌した典型的な元都会派OL。
コロナ前までは頻繁に海外を旅していましたが、近年、両足に人工股関節手術を受けました。
昨年会ったときに比べて回復が進んでいたので安心しましたが、5年以内に同様の手術をすると医師に宣告されている私にとっては、戦友のような思いです。
☆☆代ちゃんは、バッテンを2つ保持するかっこいい女性。
若い頃は実家に上がり込み、☆☆代ちゃんの妹と3人でタバコの煙とコーヒーの香りを絶やさず、朝までよくしゃべり倒したものです。
また、お互いの母同士も、とても仲が良い間柄です
男性チームの相方である☆☆☆っちゃんは、若い頃から寝る間を惜しんで働く男でした。
数年前の早朝、会社で脳梗塞を発症したものの、運良くほとんど後遺症もなく復活しました。
若くして結婚し、2人の子供に恵まれたので、上の子は既に38歳、下の子も33歳。
最近は2歳のお孫ちゃんにもてあそばれているんだ、と嬉しそうに嘆いていました。
かくいう私は、セガレがまだ19歳。
孫どころか、教育費を必死に払っている状況です。
共通点は見出せなくても、幼なじみという強い絆で結ばれているのでしょう。
55年前の偶然の出会いを、これからも大切にしていきたいと思います。
小学生だった我々も、あっという間に61歳になりました。
楽しい時間が過ぎると、最後はこう言って別れます。
「じゃあね、元気でね。」