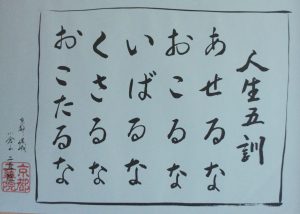そろそろ7月が終わろうとしていますが、東京では雨の日が続いています。
最も遅い梅雨明けはいつだったのだろうと調べてみると、気象庁のサイト内に「昭和26年(1951年)以降の梅雨入りと梅雨明け」というページがありました。(https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/baiu/kako_baiu09.html)
それによると、昭和57年(1982年)の「8月4日」が最も遅かったようです。
38年前の夏ですね。
私は、大学3年生でした。
ひとりでロサンゼルスへ旅立ったのは、梅雨明けの数日後だったんだなと、学生時代に想いを馳せながらサイトを見ていると、1993年だけ日付が未掲載になっていることに気づきました。
注釈によると「梅雨入り梅雨明けの時期がはっきりしなかったため、特定しなかった場合」とのこと。
こんな年もあったんですね。
今朝、テレビの天気予報を見ていると、今日の雨のポイントは「疎雨」と紹介されていました。
「そう」と読み、「疎らに降る雨」という意味だそうです。
いい言葉だなあと感じながら、雨がつく熟語を書き出してみたくなりました。
梅雨、大雨、長雨、雷雨、風雨、雨季、雨傘、雨靴、雨具、雨天、雨音、雨粒、雨男、雨女、穀雨、雨水、雨樋、時雨・・。
最後の4つは、我ながら良く浮かんだものだと悦に入りながら漢和辞典を開くと、まだまだ数え切れないほど掲載されていました。
驟雨、膏雨1)、陰雨2)、白雨、法雨、喜雨3)、雨意、雨花、雨脚、雨矢、雨施、雨集、雨師、雨飛、雨潦4)、雨涙・・。
1)膏雨:農作物をうるおし、生育を助ける雨。
2)陰雨:しとしとと降りつづく陰気な雨。
3)喜雨:夏の土用の頃、日照りが長く続いて旱ばつ状態となっている時にようやく降る恵みの雨のこと
4)雨潦:雨が降ってできた水たまり。
こういう語彙力を身に付けることは、文字を生業にする者にとって、表現力が向上しますね。
「雨」を調べたついでに、「あめかんむり」のページも読み進めると、大変興味深く、夢中になってしまいました。
雪、雫、雰、電、雷、零、需、震、霊、霞、霜、霧、露・・。
上記の見慣れたもの以外に、興味深い漢字を見つけたのです。
- 霖:【りん】ながあめ。3日以上降り続く雨。
- 霪:【いん】ながあめ。10日以上降り続く雨。「霖霪(りんいん)」も長雨の意味。
- 霤:【りゅう】あまだれ。屋根から落ちる雨水。
- 雩:【う】あまごい。雨を天に祈る祭り。また、あまごいをする。
- 霰:【さん、せん】あられ。空中の水蒸気や雨滴が凍って降ってくる粒状の氷。
- 雹:【ひょう】ひょう。雷雨などに伴って降る氷のかたまり。あられの大きなものをひょうという。
- 霙:【えい、よう】みぞれ。雨混じりの雪
- 霏:【ひ】雪や雨の、音もなく降りしきる様子。
- 霑:【てん】うるおう。うるおす。
- 靄:【あい】もや、かすみ。地表近くの大気中に霧や水蒸気の立ちこめる現象。靄然はかすみのたなびく様子。
- 霓:【げい】にじ(虹)。雨上がりの空にかかるにじ。古代には、にじにも雄雌があると考え、雄(鮮明なもの)を虹(コウ)、雌(薄い光のもの)を霓(ゲイ)といった。
漢字は奥が深く、勉強するほど楽しいですね。
漢検準一級にもう一度トライしたいのですが、60手前のアタマは、知識が留まることなくサラサラと流れ落ちるので、厳しい戦いになりそうです。