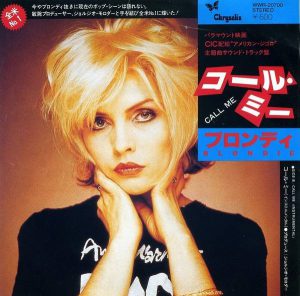フラワーショップに行くのが、少し苦手です。
どことなく照れくさい想いがあります。
花束をいただくのは、さらに苦手です(これまでの人生で花束をいただいた回数は、片手に余る程度ですが)。
初めていただいたのは、22歳の誕生日。
赤い薔薇の花束でした。
どう対処したら良いか、当惑した記憶があります。
究極は、いただいた花を抱えて電車に乗れとなったら、かなりよからぬ事態です。
浮いてる感で、車内での居心地は最悪だと思います。
これらは、典型的な時代遅れの男の姿、と言えそうです。
なぜなら、花を贈ることに恥ずかしさや照れくささを感じる男性は年々減っている、という調査結果があります。
また、バレンタインデーに花を贈る男性が増えているそうです。
バレンタインデーって男性が女性からチョコレートをもらう日でしょ! と思うのですが、これがまた昭和の男の発想のようです・・。
世界では、バレンタインデーは「男女がお互いに愛や感謝の気持ちを伝え合う日」として、主に男性から女性へ花を贈る風習が根付いているそうで、実はバレンタインデーは「世界でいちばん花を贈る日」なのだそうです。
そんな文化を日本にも広めようと、2010年に花業界が「フラワーバレンタイン」の啓発活動を始めました。
日本農業新聞によると、この推進活動によって、バレンタインデーに花を買う男性の割合が2020年には平均で7.5%となり、7年間で6倍に増えたとの調査結果を掲載しています。
特に20代の購入率が高く、若年層には既に浸透しているようです。
かくいう私も、以前に比べれば、花に対する抵抗感が少なくなってきたと自覚しています。
今年はカミさんの誕生日と母の日が重なったため、先日、2日続けてフラワーショップに立ち寄りました。
カミさんにはアレンジメントされたフラワーボックスを、そして、実母と義母にはカーネーションを購入しました。
因みに、2012年から「Mr.フラワーバレンタイン」に就任しているキングカズこと三浦知良さんは、年間で1,000本を超える赤いバラを女性に贈っているのだそうです。
スーツを颯爽と着こなし、花束が似合う男・・。
ちょっと自分には及びがたいですね。