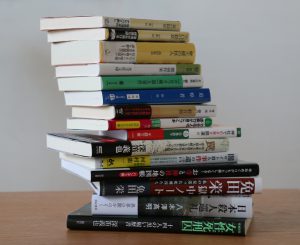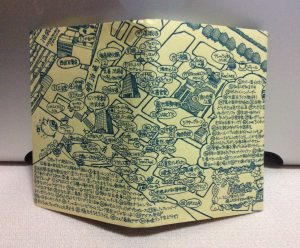今日、迎賓館へ行ってきました。
当然ですが政府からお招きをいただいた訳ではなく、天気予報が良かったので、カメラ片手にぶらりと出掛けてきた次第です。
正しい名称は「迎賓館赤坂離宮」というのだそうです。
周囲を車で通ったことは数知れずありますが、正面の瀟洒な門構えをじっくり見た記憶もないですし、ましてや、中に入ったことなどありませんでした。
まずは、早朝、人の少ない時間帯に正門を撮影しました。
警備する警官の姿もなく、静かで、厳かな冬の朝が撮れました。
公式サイトによると、正門から入ったところの前庭を見学するのは自由ですが、本館や主庭、および和風別館を見学したい場合は事前予約が必要だそうです。
迎賓館赤坂離宮では、外国からの賓客の接遇に支障のない範囲で一般公開を行っています。
急遽接遇を行う場合には、予定されていた一般公開が中止になることがありますので、御面倒でもお出かけ前に必ず下記公開状況を御確認下さい。Twitterでもお知らせいたします。
一般公開は、下記申込みページからの事前予約によるほか、事前予約なしで当日お越しの方も御参観いただけます(混雑時は、事前予約をされた方の受付が優先されます)。
早朝撮影のあと、四谷駅前のカフェで仕事に傾注し、開門時間の10時少し前に、もう一度戻ってみました。
「当日お越しの方も御参観いただけます」の一文に賭けてみたのです。
すると、予約なしでも見学が出来るとのアナウンスがあり、見学希望者は西門に案内されていました。
私もその流れに付いて行き、入口に到着すると、早くも100人以上の列が出来ていました。
そのほとんどが、予約をしていない人たち。
「今日は良い天気だから迎賓館でも見に行こうか」という都内在住者が多いのでしょうね。
私もそのひとりです。
列に並んで持ち物検査やペットボトル・水筒のチェックなどを受け、入場券(1,000円)を買うまでに10分ほど要したでしょうか。
ようやく、本館の中に入ることができました。
そこは・・、
案にたがわず・・、
日本にいることを忘れてしまうような世界でした!
家具、シャンデリア、天井、壁、鏡・・、その全てが、圧巻でした!!
廊下や階段の壁は白。
そして、その壁はどこまでも真っ白で、汚れや剥げは一切見当たりませんでした。
撮影は固く禁止されていますので、画像で紹介することが出来ず、残念です。
花鳥の間には、先月来日したトランプ大統領夫妻との晩餐会の写真が、掲示されていました。
なるほど、ここで一席設けられたのか・・と思うと、その場所にいることが、ちょっと不思議に感じました。
個人的には、天井の大絵画と高さ3メートルのシャンデリアが印象的な「羽衣の間」が最も感動的でした。
本館の見学を終え、主庭へ向かいました。
青空と白い本館が、見事なコントラストでした。
噴水越しの写真はネットでも頻繁に見ることができますので、ちょっと斜めから撮影した写真を掲載します。
早朝の撮影時は寒かったものの、徐々に気温が上がり、この写真を撮った頃には麗らかで心地よい陽気になっていましたので、見学者の数もぐんぐん増えているようでした。
なお、迎賓館は、特別開館を行っているのだそうです。
再度、公式サイトをご紹介します。
迎賓館赤坂離宮は、これまでは、来日した各国の賓客を接遇(おもてなし)する施設として、内閣総理大臣や衆参両議院の長など限られた国の機関しか利用できませんでした。 しかしながら、平成28年度より、国有財産を有効活用する観点から、接遇がないときに、下記1の要件を満たす民間企業や民間団体等も下記2の要件の満たす行事を行う場合には、原則として有償により、「特別開館」という仕組みで迎賓館を利用できるようになりました。
即ち、一定の条件を満たせば、一般人でも使用できるのです。
しかし、よくよく確認してみると、「下記1・2の要件」というのが非常に厳格で、私のような下々には全く縁がなさそうです。
ただ、民間の利用を許可した点は、評価したいと思います。
「有償」が果たしていかほどなのかも、興味がありますね。