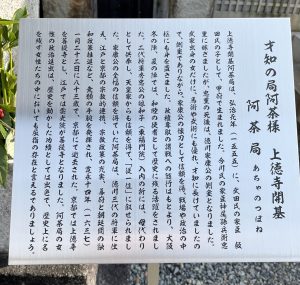初めて勝った馬券は、高校2年か3年の天皇賞秋で、枠連1-8を1,000円購入。
結果は1着トウショウボーイ、2着グリーングラス。
見事的中し、配当は1,100円で、10,000円儲かった。
自分の馬券デビューについて、上記のように確信を抱いていました。
しかし、調べてみると該当するレースが見当たりません。
そもそも、トウショウボーイもグリーングラスも、天皇賞秋を制していないようなのです。
何が合っていて、何が誤っているのか、情報を整理してみました。
レースは天皇賞秋なのか、勝ち馬をテンポイントと勘違いしてはいないか、枠連1-8は本当なのか・・・・。
思案の末、最も信頼に値しそうなのは「ちょうど10,000円利益が出た」という点ではないかという結論に達しました。
初めて購入した馬券が的中して実入りがあった訳ですから、金額に関する記憶は正確なのではないかと目星を付けたのです。
そこから探っていくと、該当するレースがありました。
1978年11月に行われた第78回秋の天皇賞の枠連配当が、1,100円でした。
私が高校2年生のときですから時期も合っていますし、レース名も合致しています。
ただ、勝ったのはテンメイ、2着はプレストウコウ、枠連は6-8でしたので、ここは記憶と相反しています。
枠連ですから、同じ枠に同居していた馬を調べてみましたが、トウショウボーイもグリーングラスも出走していませんでした。
結局のところ、納得のいく結論は導き出せませんでした。
ただ、人間の記憶は当てにならないものなんだなと、改めて思い知らされました。
因みに、未成年は馬券を購入してはならないと法律で定められています。
まあ、45年も前のことですから時効でしょう。
元来、ギャンブルは嫌いな方ではないかな、と自認しています。
思い出深いのは、大学3年の夏に行ったラスベガスです。
ロサンゼルスでホームステイをしていた私は、週末を利用してラスベガスとグランドキャニオンへ遊びに行きました。
同じツアーに参加していた仲間の多くも一緒でした。
いつかは行ってみたいと憧れていたカジノの聖地は、まさにエキサイティングでした。
この日のために日本から持ってきた一張羅のスーツに身を包み、砂漠地帯でGolden Nuggetの看板を見たとき、これまで経験したことのない高揚感を感じました。
カジノにはスロットやポーカー、バカラ、ルーレットなど多様なゲームがありますが、私はブラックジャックの魅力に溺れました。
minimum bet 1$の最もハードルの低いテーブルとはいえ、ディーラーと対峙していると、自分がすっかり大人になったような気分になりました。
ディーラーが1枚目にエースを引いた時に聞かれる『insurance?』や、『stay』『hit』を手の仕草で表現するなど、現地で遊びながら学んだことも多く、時間を忘れて没入していました。
日付変更線を過ぎた頃、やや引きの弱い男性のディーラーがやってきました。
ここが勝負どきと判断し、賭け金も増やして巻き返しに成功しましたが、その後に現れたスレンダーでクールな女性ディーラーに屈し、結局一晩で270$の負けを喫しました(この記憶もあてにならないか・・・・)。
当時の為替レートは1$270円ですから、約7万円の損失です。
40年以上前に学生が一晩で7万円も失うとは、由々しき事態であることに間違いありません。
そろそろ退散しようかなと時計を見ると、深夜2時を過ぎていました。
10人ほどの仲間とカジノに来たのですが、周りを見渡すと、友人は誰もいません。
と思ったとき、ルーレットのテーブルにいた日本人と目が合いました。
京都大学文学部3年のNちゃんでした(女子です)。
『まだいたんだ』
『国立大学の学生って、ギャンブル好きなんかね?』
深夜のカジノで聞く関西弁はすこぶる印象的でした。
あれから40余年、現在の私は、一切ギャンブルをしません。
競馬、競輪、パチンコを始め、宝くじやロト、株も含めて全く興味が薄れてしまいました。
加えて、タバコをやめて約20年、酒は生まれつきの下戸。
なんだか味気ない男ですね・・。
ただ、ラスベガスは、もう一度訪ねてみたいです。
深夜までカジノに興じる体力は失われてしまいましたが、年齢なりの違った楽しみ方ができるかなと思っています。
初めて馬券を買ってから45年。
本日、15時40分、第168回天皇賞(秋)の発走です。