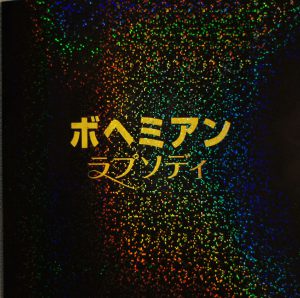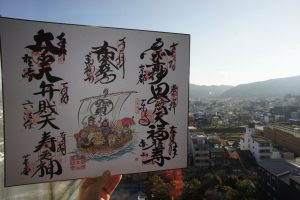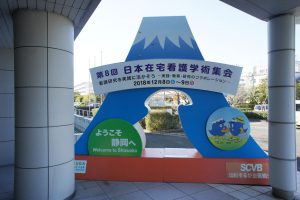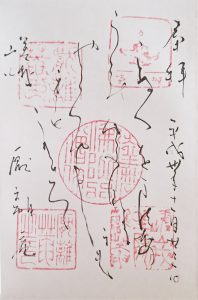先週末は、仕事にプライベートに充実した時間を過ごすことができました。
まず土曜日。
セガレの通う高校(中高一貫の男子校)で、体育祭が開催されました。
生徒たちは入学時に与えられた赤・白・黄・青の4色に分かれて、優勝目指して戦います。
この色は、卒業まで変わることはありません。
各色とも縦に4分割されるので、中1から高3までが団結しなければなりません。
その旗振り役を担うのは、「4役」と呼ばれる高3の幹部です。
団長・副団長・応援団長・副応援団長によって構成される4役は、その色の象徴的存在であり、その年の体育祭の顔でもあります。
4役はじめ高3の役員らは、年の離れた後輩たちに、競技ごとの秘策や心構えなどを熱血指導します。
「高3になったら4役になる」と心に秘めてきた役員たちですから、体育祭への思い入れは生半可なものではありません。
勝っても負けても、4役らの熱き思いは、下級生へ引き継がれていきます。
なお、高3だけは、体育祭当日に限り、髪を自分の所属する色に染めることが許されます。
そして、この「色」に対する意識は、卒業後も続きます。
私のお客様で、セガレの大先輩にあたる医師がいらっしゃいます。
その先生に入学の報告をしたところ、
「合格おめでとう!で、何色?」
と質問されました。
何組?とか、担任は誰?とか聞く前に、まず色を確認するのが通例であることは事前に抑えておいたので、「青です!」と即答できました。
以前、学校主催の講演会に参加した際、登壇した同校OBの演者がこう自己紹介していました。
「昭和☆年卒の☆☆☆☆です。あっ、色は赤です。これを言わないとダメですよね。」
これを聞いた途端、会場にいた赤組の現役学生から、大きな拍手が湧きました。
同窓が絆を深めるツールとしては、簡単明瞭でとてもいいなと思います。
さて、体育祭当日。
天気は晴れたり曇ったりの運動日和。
セガレの所属する青組は優勝から8年間遠ざかっており、入学後の成績は、4位、2位、4位。
チャンスは今年を入れて3回。
在学中に優勝を経験できなかった先輩たちの無念な思いも抱いて、ぜひとも今年は栄冠を勝ち取って欲しいものです。
果たして、結果は・・・・、
848点を獲得した、青組が優勝しました!!
ただ優勝だけを目指してきた青い髪の少年たちは嬉し涙を流し、最大5つも年の離れた後輩たちと勝利の喜びを分かち合う姿は、青春そのものでした。
一方、応援席では、運営のサポートに尽力した高3の母親たちも、抱き合って号泣していました。
たかが子供の体育祭、では片付けられないドラマを見た気がしました。
私とカミさんにとっても、初めて勝利の余韻に浸りながらの帰路になりました。
せっかくだからと、少し遅れて下校したセガレと渋谷で待ち合わせ、家族3人でささやかな祝勝会を開きました。
そして、翌日曜日。
6時30分に起床し、すぐに仕事に取り掛かりました。
例年、体育祭ではギラギラの太陽に体力を奪われ、その翌日はボロ雑巾のようになってしまうのですが、今年は曇りの時間帯もあったためか、元気に日曜日を迎えられました。
それでも、体育祭をただ座って見ていただけ、もっと言えば、一番気温の上がる時間帯には食堂へ避難して居眠りをしていたにも関わらず、太ももの筋肉痛を抱えながらの仕事となりました。
長椅子に座っていただけで、どうして筋肉痛になるのか理解不能ですが、朝から仕事に向き合えたので良しとします。
そして、午後は、東京国際フォーラムで「葉加瀬太郎・高嶋ちさ子・古澤 巌〜3大ヴァイオリニストコンサート 2019〜」を鑑賞しました。
素晴らしい演奏と、高嶋ちさ子さんの毒舌トークについては、またの機会に書きたいと思います。