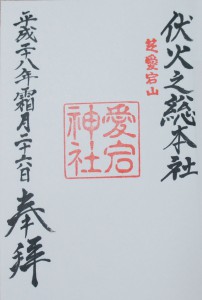明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い申し上げます。
上の写真は、昨年も紹介した弊社近くの深川資料館通り商店街に毎年出現する正月飾りです。
どんなイラストが飾られるのか、私の年末の楽しみになっています。
今年は、大きなニワトリのバックに雪をかぶった富士山。そして、松竹梅が描かれています。
江戸時代に貯木場として栄えた地に相応しい、新年に打って付けの目出度い装飾ですね。
お正月を彩ってくれる、地元商店街の皆様に感謝したいと思います。
話は変わりますが・・、
去る1月3日、セガレが1年前まで通っていた学習塾へ、久しぶりに顔を出しました。
目的は、中学受験がすぐ間近に迫った現役生を励ますためです。
自分が生徒の時にも、折に触れて先輩方が激励に来てくれたそうです。
合格の秘訣や失敗談を話してくれたり、入学後の中学生活について聞かせてくれたり、帰り際には、お菓子を配ってくれたのだそうです。
この時期、世間がお正月モード全開なのに対して、「正月特訓」真っ只中の現役生は、お正月気分に浸ることも許されず、塾の休みは元旦だけ。
セガレが受験生の前で有益な話ができるとは思っていませんが、受けたご恩をお返しし、人のために時間を使うことの大切さを教えるには絶好のタイミングと思い、差し入れ用に合格祈願の定番お菓子「キットカット」を買って、塾に向かわせました。
塾が指定した時間は、午前最後の授業がそろそろ終わりに近づく頃でした。
セガレの出番は、生徒たちがお弁当を食べ終わり、午後の授業が始まるまでの時間帯です。
時間が来るまで事務室で待機し、その後、教室で15人ほどの後輩の前で話をしたそうです。
自宅に戻ってから話を聞くと、事務室で待っている間、塾長をはじめ、多くの先生方がセガレを覚えていてくれて、様々お話しが出来たのだそうです。
11ヶ月ぶりに顔を出した卒業生を快く迎えてくれ、先生と生徒という関係でなくなった今もご縁を繋げてくださったことを、とても有難く思いました。
また、偶然にも塾長はセガレの学校の先輩にあたりますので、塾長が通っていた頃の学校と現在との違いなどについて、具体的にお話し出来たことも楽しかったようです。
かつて、遊びたい盛りの小学生を塾に通わせることの是非について迷ったこともありますが、我が家にとっては間違っていなかったのかな、と思いました。
「ご縁」という言葉が私は好きです。
英語にすると「meeting」とか「chance」などが該当するのでしょうか。
でも、微妙なニュアンスが伝わらないですね・・。
やっぱり、日本人に生まれて良かったな、と思います。